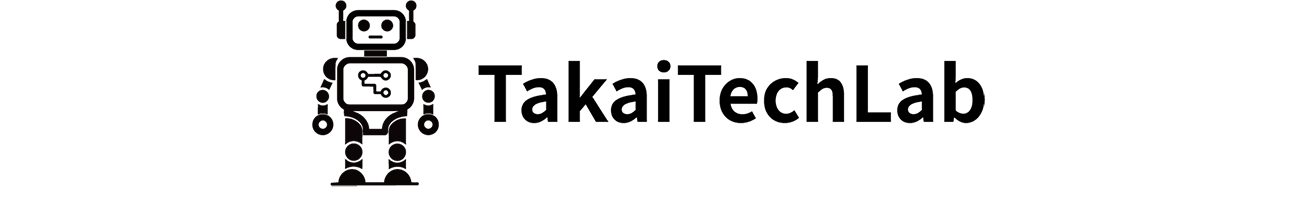電気回路の初めての記事になります。
今回は、電気回路とはどういうものかを説明していきます。
電気とは
電気には、粒子があり、プラスの性質を持つ陽子と、マイナスの性質を持つ電子があります。
電気とは、電子が動いたり、集まったりすることで起きる現象のことです。
では、この電子はどこにあるのでしょうか。
電子は、私たちの身の回りのあらゆる物質をつくっている「原子」の中にあります。
そして、私たちの身の回りにはすべて原子という小さな粒でできています。
例えば、木や水、空気、金属、ガラス、プラスチックなど、形や性質が違うものでも、すべて原子が集まってできています。
原子は、中心に「陽子」と「中性子」があり、その周りを「電子」が回る構造をしています。
この電子が動くと電流になり、電子が特定の場所に集まると静電気が起こります。
電流を流す力(電圧)
電流とは、電子という小さな粒が流れることです。
しかし、電子は自然には流れません。
そこで、電子を押し出して流れをつくるための力が必要になります。
水の流れに例えるなら、水を押し出すポンプのようなものです。
この押し出す力を 電圧(でんあつ) と呼び、単位は ボルト[V] で表します。
電流の流れにくさ(抵抗)
電圧は、電子を押し出す力でした。
では、押し出された電子がどれくらい流れるかは何で決まるのでしょうか。
実は、電子の“通り道の状態”によって流れる量が変わります。
水のホースでも、太いホースはたくさん流れ、細いホースは少ししか流れません。
電気も同じで、電子が流れにくいほど電流は少なくなります。
この「流れにくさ」のことを 抵抗 といい、単位はオーム[Ω]で表します。
電気回路とは
電子が流れるためには、ぐるりと一周できる道が必要 です。
この電子の通り道をつくったものを 電気回路 といいます。
水で例えるとイメージしやすくなります。
バケツ、ポンプ、蛇口、ホースを用意し、ホースの両端をバケツにつけるとします。
- バケツの水をポンプでくみ上げる
- くみ上げた水を蛇口からホースへ流す
- ホースの先から再びバケツへ戻る
このように、水がぐるっと1周できる状態が「水の回路」です。
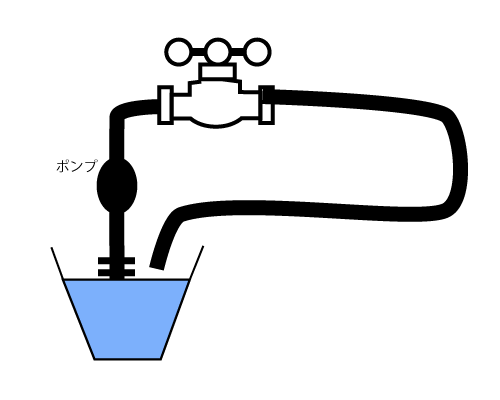
そして、ホースを途中で押さえると水の流れる量が減ります。
この「流れにくさ」が電気でいう 抵抗 にあたります。
水の回路を電気回路に置き換えると
水の回路を電気回路に置き換えると次のようになります。
- ポンプ → 電圧(電気を押し出す力)
- バケツ → 電源(電池やUSB)
- ホース → 電線
- 蛇口 → スイッチ
- ホースを押さえる → 抵抗(流れにくさ)
このように、水の流れの仕組みと電気の流れの仕組みはとてもよく似ています。
電源(バケツ+ポンプ)と電線(ホース)でぐるっと一周できる道を作ることで、はじめて電流が流れます。
まとめ
- 電気とは、電子(マイナスの粒子)が動いたり集まったりすることで起きる現象。
- 電子は原子の中にあり、原子は身の回りのすべての物質をつくっている。
- 電流は、電子が一定方向に流れること。
- 電圧は、電子を押し出す力で、ポンプのような役割。
- 抵抗は、電子の流れにくさで、ホースを細くしたような状態。
- 電気は、ぐるりと一周できる“道”を作らないと流れない。
- この電子の通り道を作ったものが電気回路である。