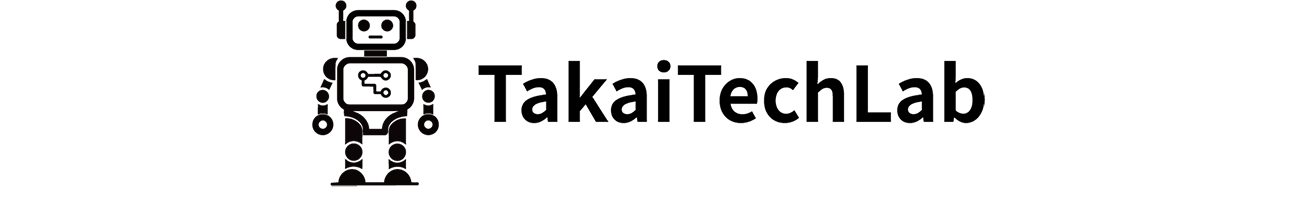電気回路を扱ううえで、最も基本となるルールが オームの法則 です。
IoTの現場では、LEDを光らせるとき、センサーを接続するとき、マイコンのGPIOを保護するときなど、あらゆる場面で必ず使います。
今回は、初心者でも理解できるように、オームの法則を丁寧に解説します。
オームの法則とは
オームの法則を水の回路に例えて考えてます。
水の回路が、バケツ、ポンプ、蛇口、ホースで構成されているとします。
ホースの両端はそれぞれバケツに入れます。
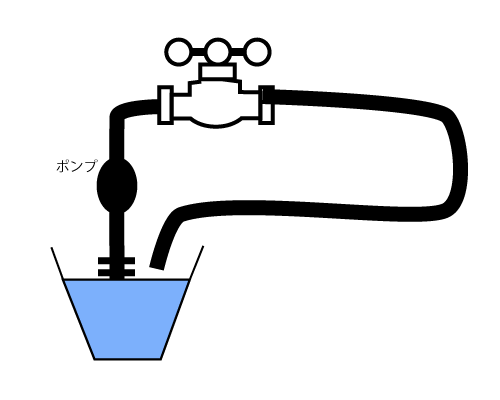
ポンプの強さ(電圧)を2倍にすると、流れる水の量(電流)は2倍になります。
ポンプの強さは通常にしておき、ホースを細くして抵抗を2倍にすると、流れる水の量は半分になります。
つまり、電圧と電流は比例し、抵抗と電流は反比例していることがわかると思います。
この関係を式で表すと、抵抗R[Ω]に電流I[A]が流れているとき、抵抗にかかる電圧V[V]は、
電圧V[V]=電流I[A]×抵抗R[Ω]
となります。
この法則をオームの法則といいます。
電圧、電流、抵抗の3つの値のうち、2つが分かれば、残りの1つが必ず計算できます。
- 電圧を求めたい → V = I × R
- 電流を求めたい → I = V / R
- 抵抗を求めたい → R = V / I
抵抗は変化しない
オームの法則では、抵抗値は一定で変化しない ことが前提です。
電圧 10V の電源に、抵抗 2Ω の電球をつなぐと、流れる電流 I は、
I = 10V ÷ 2Ω = 5A
次に電圧を 2倍の 20V にすると、
I = 20V ÷ 2Ω = 10A
となり、電流が2倍 になります。
ここで変わっているのは 電流だけ です。
抵抗(2Ω)は決して勝手に変化しません。
- 電圧を変える → 電流が変わる
- 抵抗は固定値の部品
という部分をしっかり押さえておきましょう。
オームの法則が当てはまらない
すべての電圧、電流、抵抗がオームの法則に当てはまるわけではありません。
例えば、ダイオードやLEDは、ある電圧を超えると急に電流が流れるという性質を持っている部品です。
この場合、電圧を2倍にしても、閾値を超えなければ電流はながれませんし、超えると急激に電流が増えます。
このように電圧と電流が比例しない部品では、オームの法則は成り立ちません。
オームの法則が成り立つのは、電圧と電流が常に比例するような普通の抵抗器の場合に限られます。
まとめ
- オームの法則は V = I × R
- 電圧と電流は比例、抵抗と電流は反比例
- 抵抗値は変わらない(固定値の部品)
- LEDやダイオードなど、オームの法則が適用できない部品もある
- IoTではLEDやセンサーを扱う際に必須の知識