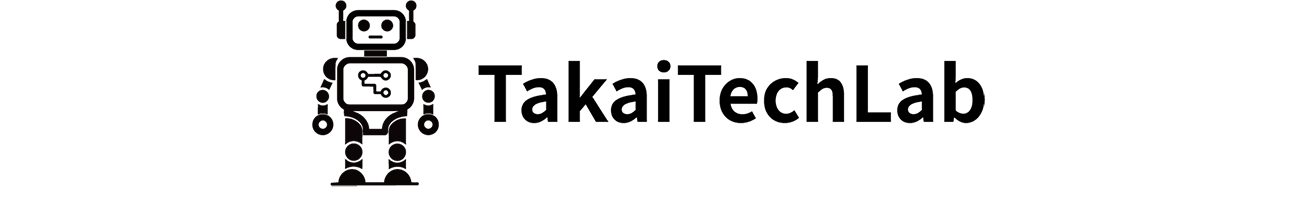前回は、電気とはどういうものか、電気回路とはどういうものかを説明しました。
今回は、電流の流れる向きや電流の特徴を解説します。
電流の流れる向き
電気(電流)は、プラス極からマイナス極に流れるとされています。
しかし、実際に動いているのは電子で、電子はマイナス極からプラス極に流れます。
このような違いが生じたのは、歴史的な経緯によるものです。
昔は、電気の正体がわからないまま、電流はプラス極からマイナス極に流れるということが先にきめられてしまいました。
その後の研究で、電子がマイナス極からプラス極に流れていることが判明したのです。
しかし、プラスの電荷がプラス極からマイナス極に流れることと、マイナスの電荷がマイナス極からプラス極に流れることは、同じと扱っても、計算結果や回路の動作にほとんど影響を与えなかったことから、電流の向きの定義は変更されず、今に至ります。
(実際に、プラスの電荷が電子のように移動することはできないため、プラスの電荷が電線を流れることはありません。)
電流の特徴
電気回路に分岐や合流がなければ(1本道であれば)、電線のどの部分も同じ大きさの電流が流れます。
これは直列回路の大きな特徴です。※直列回路については、別記事で説明する予定です。
電流の大きさ
電流の大きさは、1秒間に電線の断面に流れる電荷の量のことです。
電荷の量は、クーロン[C]という単位で表します。1クーロンの電子の数は、約624京個です。
そして、1秒間に何クーロン流れるかを表す単位として、私たちがよく見かけるアンペア[A]を用います。
1[A] = 1秒間に1[C]が流れる
2[A] = 1秒間に2[C]が流れる
ということになります。
なぜ1クーロンが624京個なのか?
もともと、1秒間に1アンペアの電流を流し、その間に運ばれる電荷の量を1クーロンと決められました。
そして、その間に運ばれた電荷の量が624京個の電子だったというわけです。
1アンペアはどうやって決めたのか?
それでは、1アンペアはどのように決められたのかと疑問が出てきますね。
昔は、電子の数がわからなかったので、「電流の大きさをある値に固定すれば、毎秒これだけ銀が析出する」と再現できたため、この量を基準に1アンペアと決めたそう。
電流が流れる条件
電流は回路を1周できないと流れることはできません。
したがって、回路の途中で電線が切れると、水路の蛇口を閉めて水が流れなくなっている状態と同じです。
ただし、回路を1周できるように繋いだとしても電流は流れません。電流が流れるためには、電源(電圧)が必要です。
電源を切った状態だと、自由電子が各自バラバラの方向に動いています。
そこに電源から電圧をかけることにより、自由電子はみな同じ方向に動き出し、電流となります。
また、電子が動きやすい線(銅線など)で繋がっている必要があります。
ゴムなどでは、電子が動けないため、電流は流れません。
電子が流れる速さ
電子の流れる速度は、実は遅く、0.1mm/秒です。1分で6mmしか進まないことになります。
では、なぜスイッチを入れるとすぐにライトが付いたりするのでしょうか。
それは、電子1つが電源からライトまで走っていくわけではないからです。
電線には、自由電子が詰まっています。そして、電子の押し出す力が一瞬で伝わり、ほぼ一斉に電子たちが動き出すことですぐに動き始めることができるのです。
電子は電界の影響で動く
電源を付けると、電子を動かす力が回路全体に伝達されます。
この電子を動かす力を電界といいます。
電界は1秒間に光に近い速さで伝達されます。
その力を受けて電子が動き始めることになるため、電子の移動が遅くても、電気の反応は一瞬で起きるように見えるのです。
まとめ
- 電流とは、電子が一定方向に流れることで生じる現象。
- 電子はマイナス極からプラス極に流れ、電流はその逆方向で考える(約束事)。
- 分岐や合流のない直列回路では、どこでも同じ電流が流れる。
- 電流の大きさは、1秒間に流れる電荷(クーロン)の量で決まる。
- アンペア[A]は、1秒間に何クーロン流れるかを表す単位。
- 電流を流すには、電圧・閉回路・導体(電子が動ける物質)が必要。
- 電子の移動速度は遅いが、電界が一瞬で広がるため電気の反応は速い。
- 電流が多すぎると部品が壊れるため、安全には抵抗が重要。